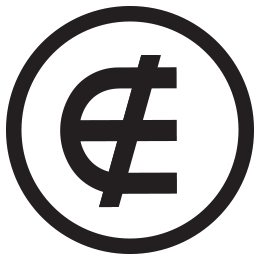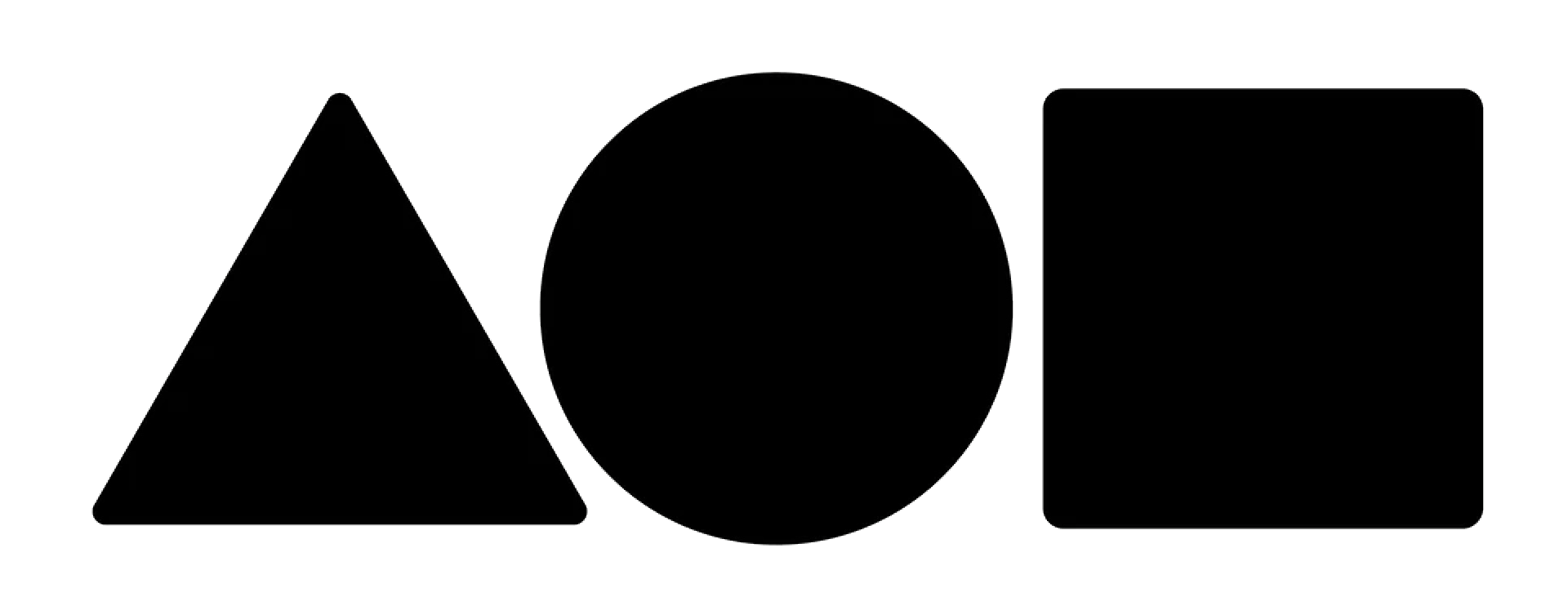STORY01
STORY02
STORY03
SWIMMING POOL
CAFÉ
CAFÉ
その街はどこにあるのか。
アジアの都市か、ヨーロッパの都市かもしれない。
風景からかろうじてわかるのは現代の大都市であるということだった。
∉
カフェの入口につづく階段を登ると、コーヒーの匂いがする。
それは記憶の底に沈んでいた、忘れていた何かを一瞬引き上げる。
私はテーブルのそばに腰を下ろした。
隣の席にこれまで見かけたことのない人が座った。
その人が近づくたびに、時間が歪んだ気がした。
髪の毛から覗く耳は
自分の垂れた耳と違う形をしている。
「同じ朝は存在しない」
その人はサングラスを外しながら煙のようにくぐもった声を出す。
「毎日、似た夢ばかりみるが」
チェスの駒を動かしながら私は答えた。
「ところで、あなたに名前はあるのか」とその人が訊いてきた。
「昔はあった。でも今はない」
「名前を捨てたのか、失くしたのか。それとも盗まれたのか」
答えられない。
どれも、正しく聞こえる。
「間違いはいつもある部分は正しい」
∉
「この都市の記憶は食べ残しに似ている」
その人は何も言わずにじっと見つめてくる。
目で言葉を伝えてくる。
「これは、自分の言葉じゃない。ある人が言っていた言葉」
ある人の口から出た言葉が、他人の耳で誰かのものになる。
都市はそういうふうに作られている。
「コーヒーは好きか」と私はその人に聞いた。
「沈黙に合う。苦いけど、飲み続けてしまう。人生に似ている」
「チェスは人生に似ているだろうか」
その人が訊いてきた。
「どうだろう。似ている人生もあるかもしれない。
チェス盤上では、みせかけは長くは生き残れない」
朝の光は薄く、影の輪郭はぼやけていた。
駒の影は、クロワッサンのように湾曲して盤の上に写っている。
夜の気配を含んだ朝の空気は、昼に向かって消えようとしていた。
次に駒を動かそうとした時、もうその人は居なくなっていた。